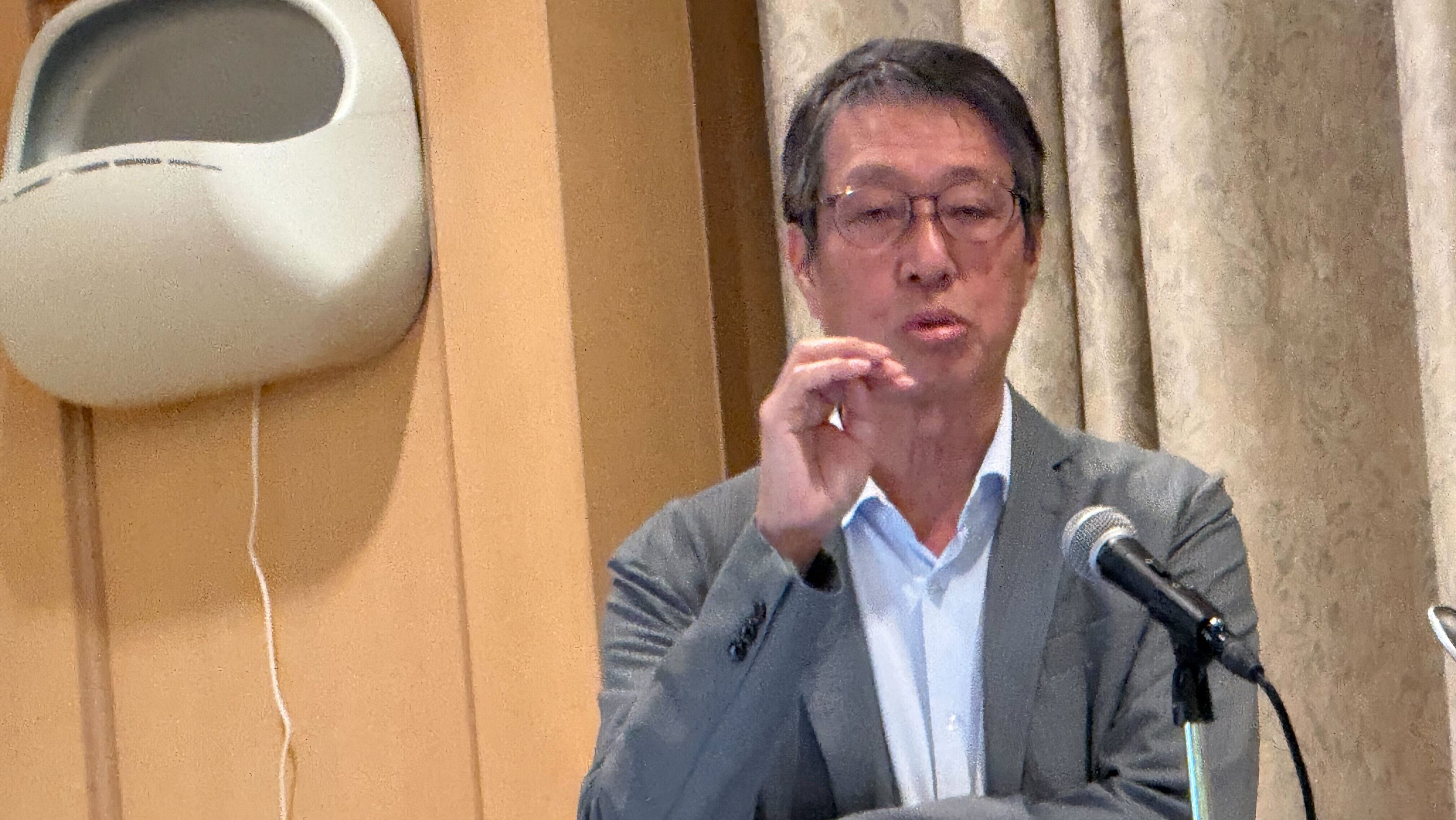見えない地下水を「みんなの知恵」で見える化する

第一工科大学・高嶋 洋 先生 講演レポ(感想つき)
最初は“地下水=むずかしい”と思っていたのに、聞き終えるころには「測れば見える。見えれば守れる」に心がスッと落ちました。しかも古い井戸を生かすという着想が、コストにも文化にも優しい。ルスツから始まる“地下の見える化”は、本当にワクワクします。
地下水は「時間で流れる」— まずはやさしい入門から
高嶋先生の導入は、ミニ講義。
地下水は雨がしみてから湧き出すまでの“時間”が層になっているのが肝。雨の翌々日に湧く流れもあれば、10〜20年、100〜1000年という長い旅路の水もある。地表からは見えないけれど、3次元でゆっくり動いている—そんなイメージがまず腹に落ちます。
ルスツの強み:火山の大地が育てた“湧水王国”
火砕流や溶岩、火山灰…火山がつくった地層は、水を通しやすいところ・通しにくいところがはっきり。
その結果、羊蹄山の東側には大規模な湧水点が点々と、西側には小さめの湧水が多数。
スケール感も圧巻で、湧水が「1日8万トン」というデータも。先生は例えに、大規模工場の取水「1日1万トン」×8社分と重ねてくれました。数字で聞くと、すごさが一気に具体化します。
「分水嶺のリゾート」— 地下はブロックが分かれているかもしれない
ルスツは分水嶺上にあります。重力異常や河川の折れ曲がりなど地形のヒントを重ねると、地下の連続性が変わる帯の存在が見えてくる。
先生はここを複数の“地下水区(地下水ブロック)”としてとらえ、区ごとに性格が違う可能性を示しました。
使い方の実像:村とリゾートの水源
ヒアリングで水源の配置と役割も整理されました。
- 村は河川取水が中心。足りないときは井戸で補助。
- リゾートは施設脇にも井戸を持ち、地域の利用と組み合わせながら活用。
結論として、「どの地下水区がどんな挙動か」を連続観測で見極めることが、将来の安心に直結すると先生は指摘しました。
新しい井戸は掘らない。あるものを生かす:「古井戸モニタリング」
新設井戸は高コスト—ここで先生の逆転の発想。
地域に点在する古井戸を観測点にして、水位センサー+通信でクラウドに連続データを集める。点を面に変えるネットワーク型の観測です。
- 住民・自治体・企業で協力して**“地下水カルテ”**をつくる
- 損害や影響を“数字”で議論できる
- 企業にとっても持続可能性(たとえばEUタクソノミー)を定量で示す強い根拠に
すでに泉川地区の浅井戸で装置を設置。7〜9月の連続データでは、夏に向けて低下→のち回復→現在は横ばいという“季節の鼓動”が見えてきました。小さなデータの積み重ねが大きな安心をつくる—この言葉が妙に沁みます。
これが効く理由:地域・企業・自然、みんなにメリット
- 地域の安心:渇水や地盤沈下の兆しを早くつかめる。取水のローカルルールも合意しやすい。
- 企業の信用:“水を大切に使っている”をデータで証明。サステナビリティの実質が上がる。
- 自然の回復力:湧水・河川・湿地は地下水と一体。流域全体の循環を守る手応えが増す。
いま、私たちにできる小さな一歩
- 古井戸の所在情報を集める(場所・深さ・普段の使い方)
- 観測候補の選定(安全・アクセス・代表性)
- データの“見える化”の場づくり(学校・公民館・オンライン)
“地下の共同管理”は所有権を侵す話ではない。みんなで測って共有する—まずはそこから始まる、という姿勢が心地よい。
まとめ(そして、もうひとつの感想)
高嶋先生の話は、専門を生活の言葉に“翻訳”してくれる講義でした。
翌々日の湧水、10〜20年の旅路、100〜1000年の時を経る水。
この時間の厚みを想像すると、ルスツの風景が少し違って見えます。
最後に
「測れば見える。見えれば守れる」。その合言葉だけ持って、古井戸から始めよう。
地図に載っていない地下の“川”を、私たちの手で描く。ルスツ発のやさしい地下水マネジメント、本当に楽しみです。