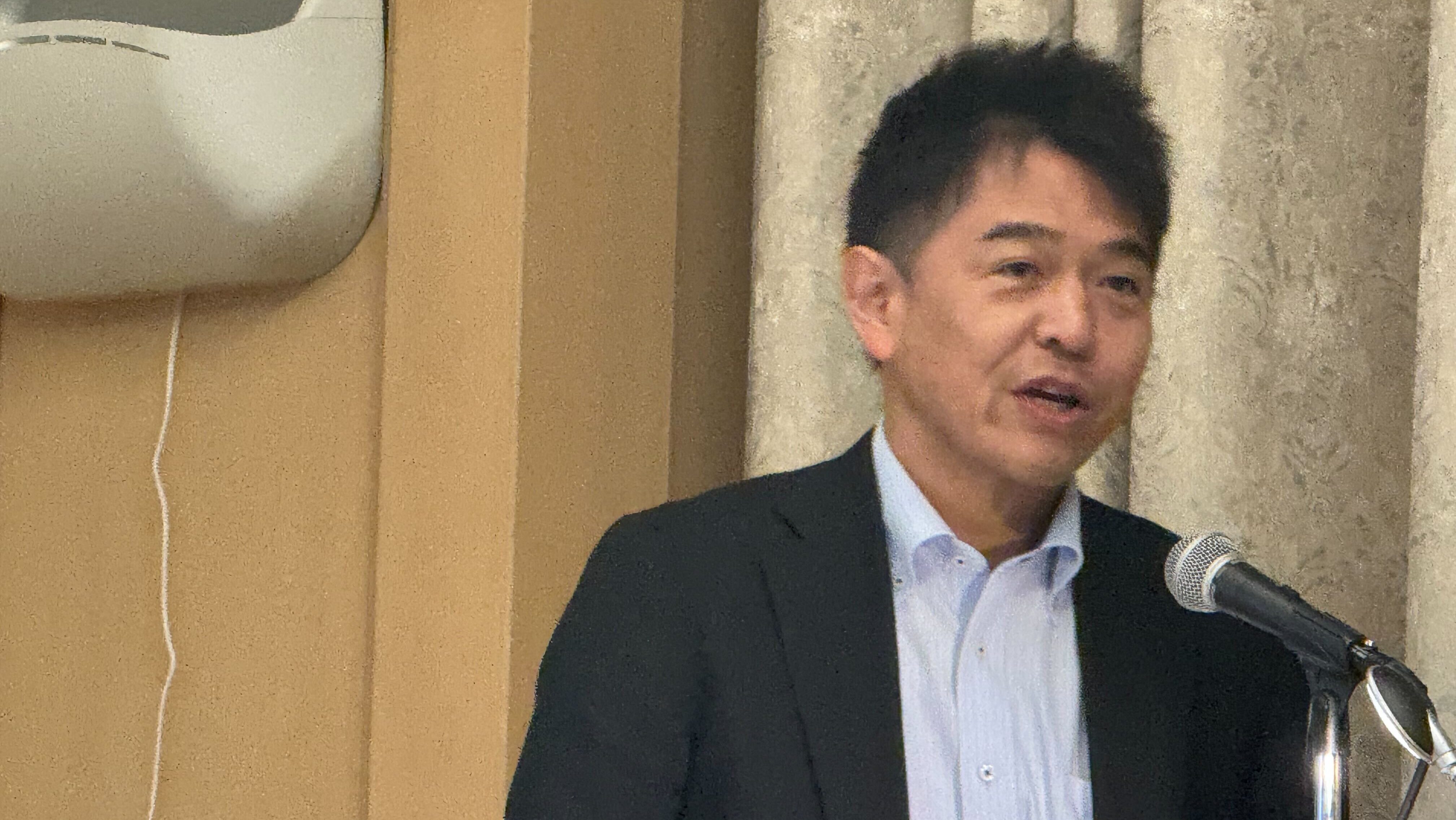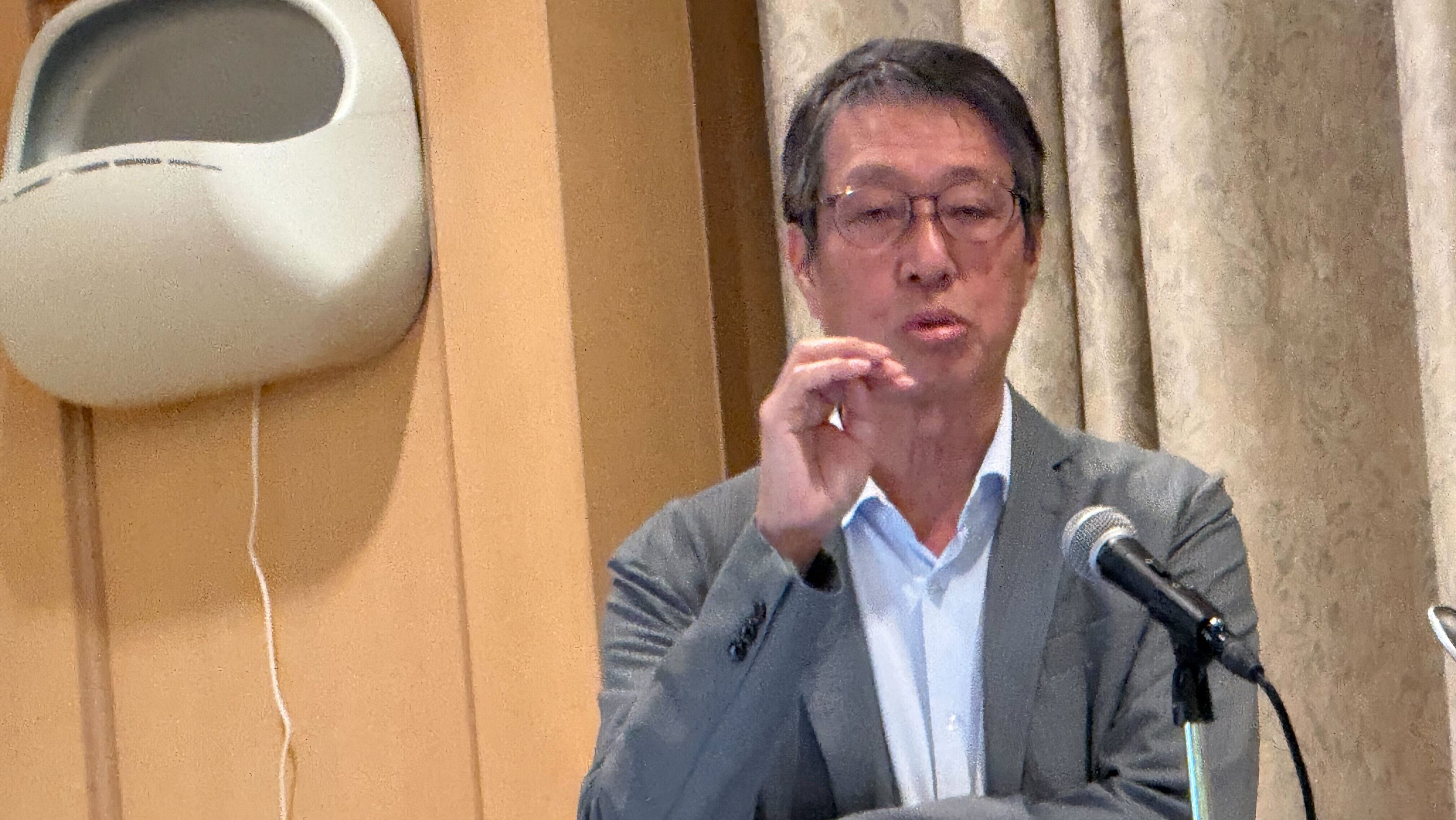第2回水循環シンポジウムを終えて

― 留寿都から広がる“水と地域”のストーリー ―
2025年9月20日、留寿都リゾートで開催された第2回水循環シンポジウムが無事に終了しました。
初回に続き、多くの研究者・自治体・企業・地域住民の方々にご参加いただき、「水」をめぐる学びと対話を深める一日となりました。
専門家の講演から学んだこと
まず心に残ったのは、島谷先生(熊本県立大学)のご講演。
「雪や雨をどう“ためて・しみ込ませて・ゆっくり流すか”が、洪水を減らし地下水を増やす鍵になる」というお話は、数字を交えた具体例でとてもわかりやすく、改めて水循環の奥深さを実感しました。
また、蔵治先生(東京大学)は、温暖化で雪の降る時期や融け方が変わりつつあることをデータで示してくださいました。これはスキー観光だけでなく、春の水資源や地下水涵養に直結する問題であり、「雪を守ることは水を守ること」だという視点が強く印象に残りました。
首長パネルに見た“現場のリアル”
午後のハイライトは、羊蹄山ろく7町村の首長・幹部が一堂に会したパネルディスカッション。
「水」をテーマにこれだけの自治体首長が集まるのは本当に珍しく、すでに水利・土地売買・インフラ老朽化などの課題が進行している現状を考えると、きわめて貴重な機会だったと思います。
- 倶知安町長は、人口1.5万人に対して年末年始の宿泊客が1.8万人を超える現状を紹介し、50〜60億円規模の水道整備に迫られていることを率直に語りました。
- ニセコ町長は、「面積×降雨量以上は汲めない」という独自条例を説明し、持続可能なルールの大切さを共有。
- 蘭越町長は、尻別川統一条例やクリーン作戦の継続を通じて「川を世話する文化」を語り、京極副町長は吹出し公園の湧水(1日8万トン)を守る取り組みを紹介しました。
それぞれの町が抱える事情は違いますが、共通するのは「水は生活であり、観光資源であり、同時に守るべきもの」という認識でした。
シンポジウムを終えての感想
第2回を終えて感じるのは、研究・政策・現場の声がようやく一つの場で交わりはじめたということです。
数字で裏付けられた研究成果と、町民の生活や観光需要のリアル、そして企業の視点が同じテーブルに乗った。これは決して当たり前ではなく、確実に次につながる一歩だと思います。また、加森社長のクロージングで語られた「北海道をワンチームに、世界に向けて発信する」という言葉が強く響きました。水は循環し、つながります。だからこそ、ノウハウも、知恵も、地域同士で循環させることが必要だと実感しました。
次に向けて
来年も必ずこのシンポジウムを開催し、進捗を確かめ合う場にしていきます。
研究データの蓄積、地下水の観測ネットワーク、条例によるルールづくり、地域住民の参画。やるべきことは多くありますが、今回見えた“共通認識”を出発点に、着実に進めていきたいと思います。
最後に
ご登壇いただいた先生方、首長の皆様、参加者の皆様に心より感謝申し上げます。
「水を守ることは、地域の未来を守ること」。その思いを胸に、留寿都から新しい循環を作っていきます。