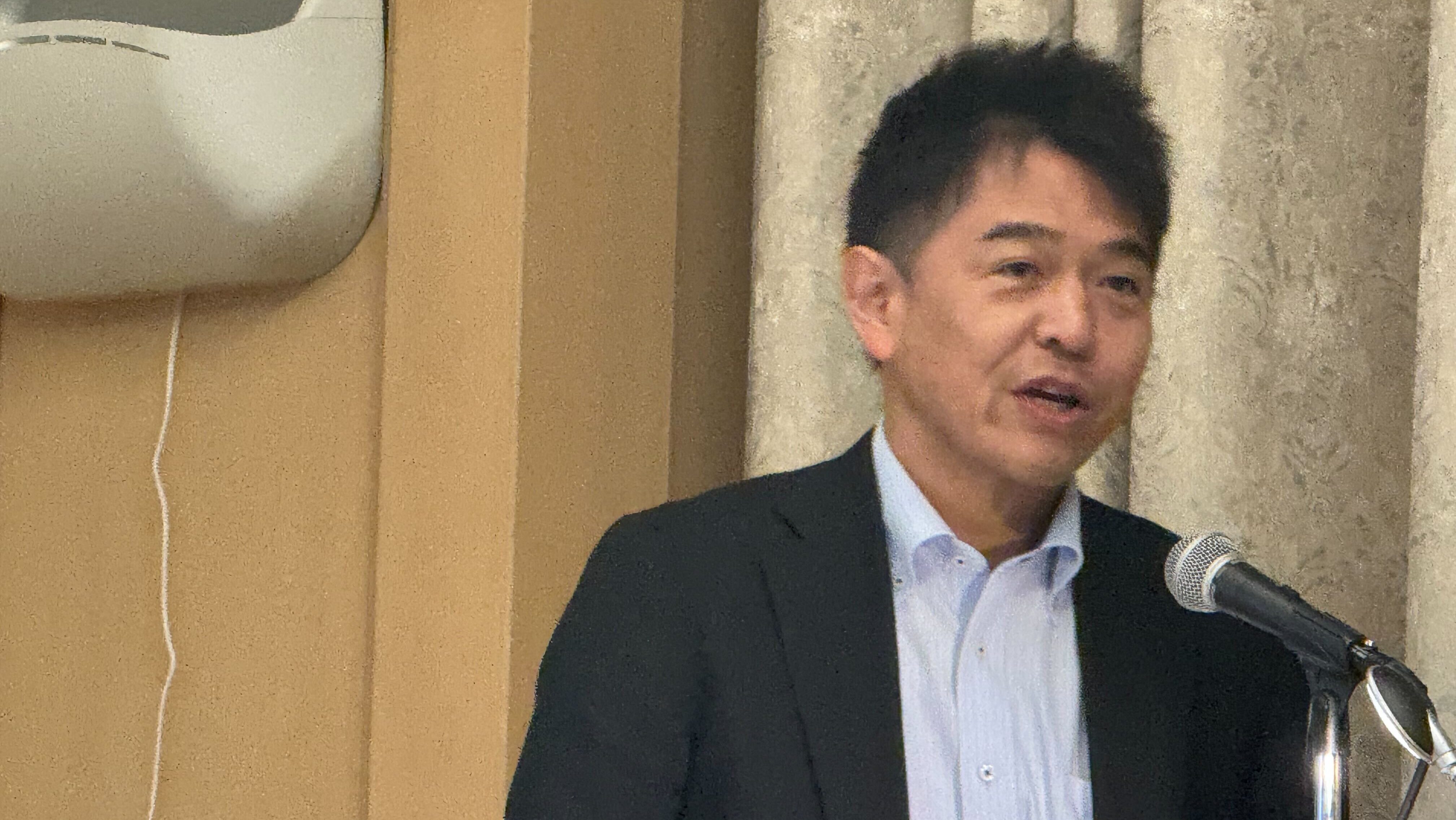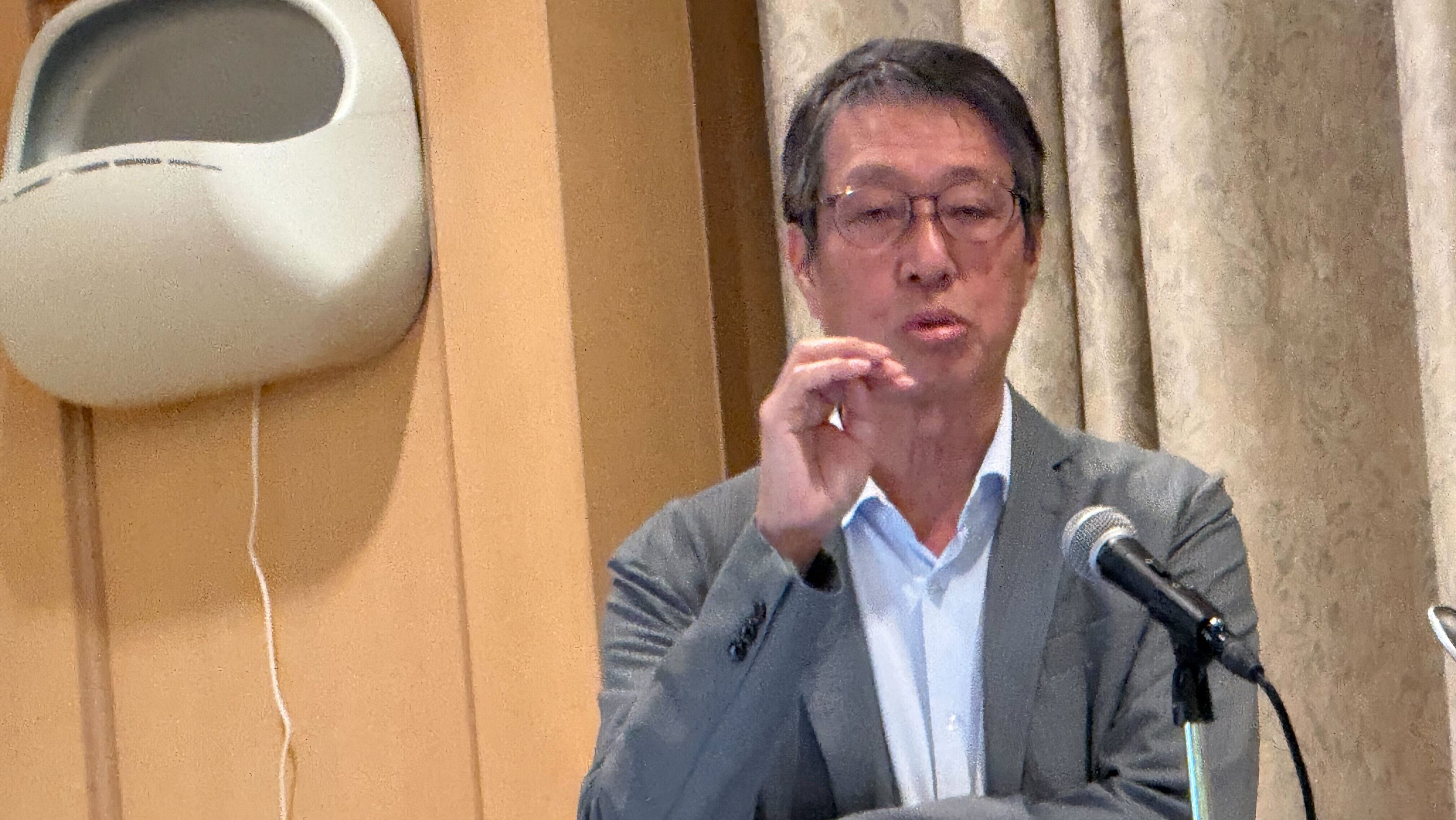「羊蹄山ろくの水を語る」

首長たちが一堂に会したパネルディスカッションを取材して
これだけの町村(留寿都・喜茂別・倶知安・ニセコ・蘭越・京極)が「水」というテーマで集まるのは本当に珍しい。水は生活インフラであり、観光資源であり、同時に利権や開発規制といった繊細な問題ともつながっている。すでに各地で水をめぐる課題は動き出しており、今回のパネルはその現実を“流域全体の視点”で共有できた貴重な時間だった。
生活と観光を直撃する「雪と水の変化」
留寿都の佐藤村長は「にぎやかになるのはありがたいが、守るための網かけも必要」と静かに語った。
一方、喜茂別の林町長は「年末は雪が多すぎて苦情、2月は逆に雪不足」という、“冬の質”の変化を率直に披露。スキー観光地にとって死活問題であると同時に、水循環のリズムが変わっていることを示す実感でもあった。
倶知安・ニセコが抱える“急成長の重さ”
倶知安の文字町長は、人口1.5万人の町に宿泊客が1.8万人泊まる現実を数字で共有。わずか年末年始のピークのために、50〜60億円規模の上水道増強が必要という話には、会場もどよめいた。ニセコの片山町長は、「面積×降水量を超える取水は不可」とする独自の水資源条例を紹介。投資や開発を拒むのではなく、ルールを明確化して持続性を確保するという姿勢が印象的だった。
川を“母なる存在”とする文化
蘭越の金町長は、7町村で制定した尻別川統一条例や、31年続くクリーン作戦を紹介。
「川を使うだけでなく、世話する文化を守り続けたい」という言葉に、この地域の誇りがにじんでいた。
京極の小林副町長は、吹出し公園の湧水(1日8万トン、年間来訪者50万人)を紹介しつつ、京極だけ水位が上がりやすい実態や深夜警戒の苦労も語った。観光パンフレットには載らない現場の緊張感が、リアルに伝わった。
会場をつないだキーワードは「つながり」
モデレーターの高嶋先生は最後にこう総括した。
「結局いちばん強いインフラは、人と人のつながりです。」
違う立場の発言が、尻別川という流域で一本につながる。そこには「対立」ではなく「調整」の空気があった。
最後に、水は循環する。町境を超え、国境を超え、時間を超えて動く。
今回のパネルは、その当たり前を「自治体がどう受け止めるか」を率直に語り合う場だった。水を守る条例、増え続ける観光客、老朽化する水道管、そして深夜に川を見守る職員。どの話も一見バラバラだが、「水を理由に、町村が手を組む」という一本のストーリーに結びついていた。
この集まりは単なるイベントではなく、すでに始まっている“流域全体の意思表示”だと思う。水をめぐる課題が深刻化するなかで、こうした会議がどれほど貴重かを強く感じた。