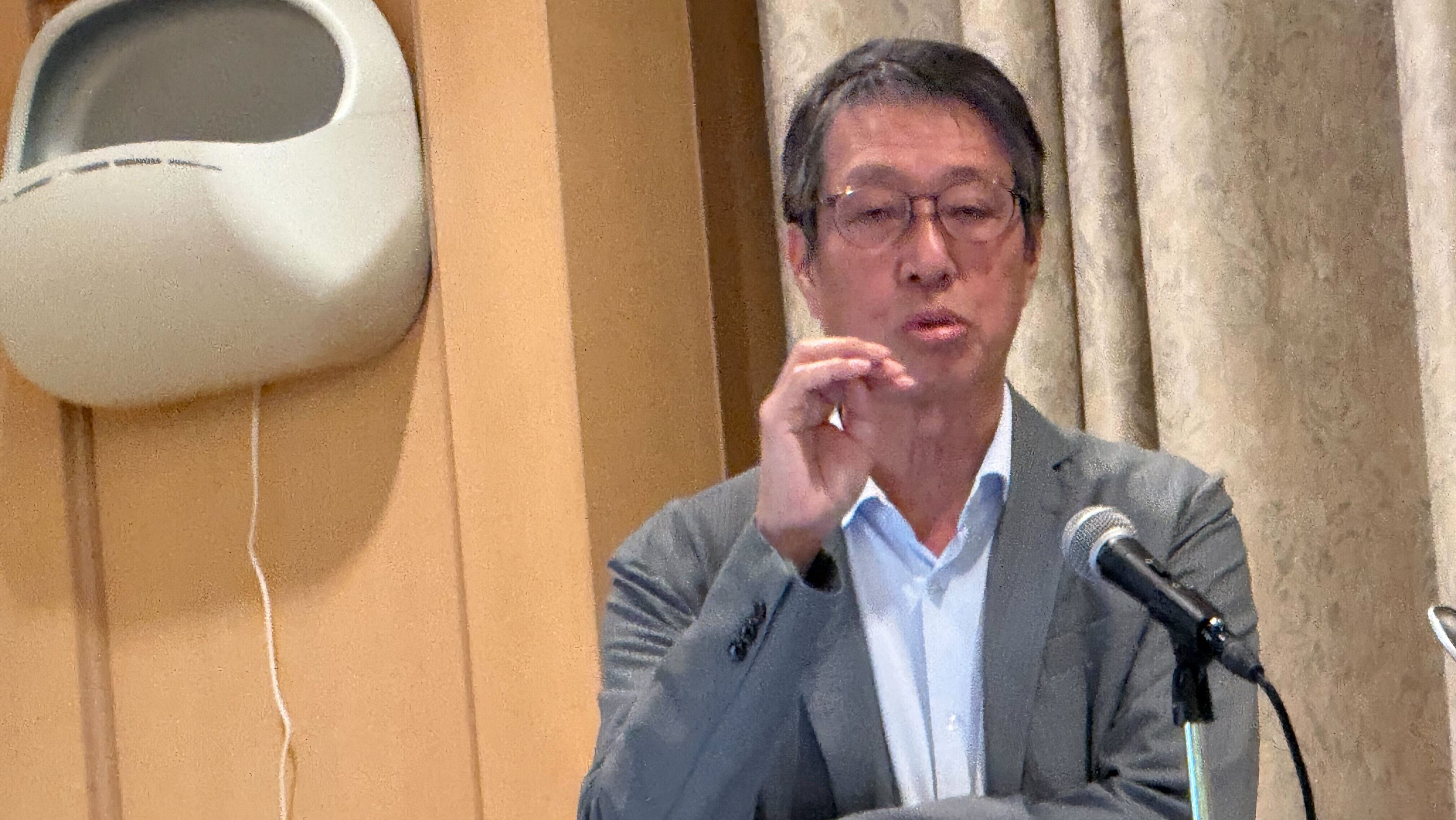「水・人・暮らし」を丸ごと回すには?
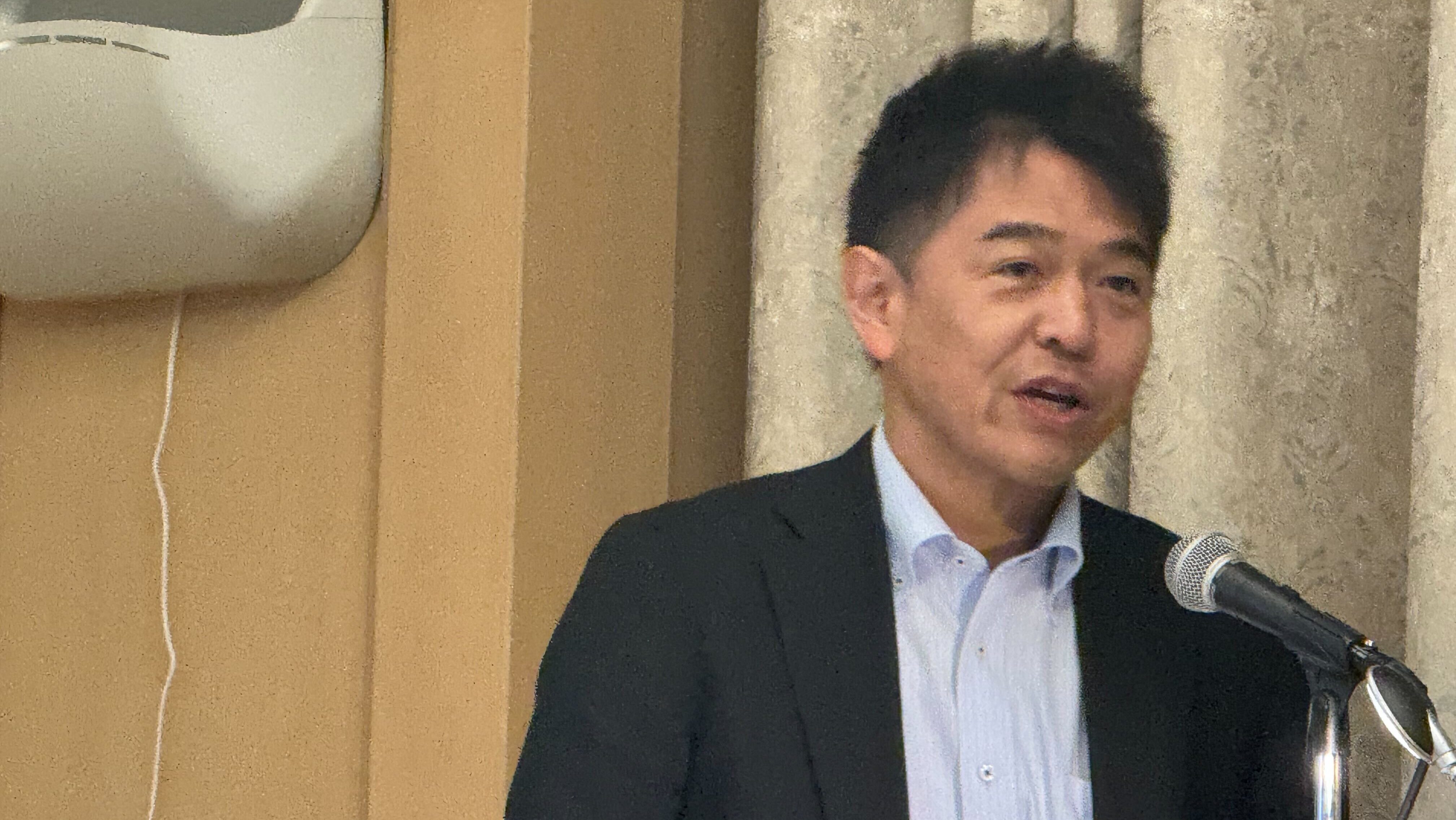
国交省・天野正治さんのやさしい水循環レクチャー(講演レポ)
「今日は水の循環を入り口に、経済の循環、そして人の循環までをつないで話します」。
国土交通省 大臣官房審議官の天野正治さんが、難しいテーマを生活目線でほどいてくれました。固い政策の話…と思いきや、中身はとても実感的。地域で暮らす私たちこそ知っておきたいヒントが詰まっていました。
まずは“いまの日本”を知る:人数だけじゃなく「どこに住んでいるか」が変わる
- 日本の人口は2008年に約1億2,800万人でピーク。今は減少中で、2050年頃は約1億人の見通し。
- 大事なのは「減る場所・残る場所の偏り」。たとえば北海道は500万人超 → 300万人超へと小さくなる予測です。
人口が1万人を切る町では、映画館や百貨店などの“あると楽しい”サービスが維持しにくい(いわゆる“スタバチャート”の話)。買い物や移動(2次交通)をどう確保するかが生活の要になります。
要は、「人数が戻る」のではなく住む場所のバランスが変わる。生活サービスをどう面で支えるかが勝負どころ。
水循環の話を「暮らし」に引き寄せる
ここ数年、“一部でドカッと降る一方、全体は雨が少ない”という極端な降り方が増えました。人口減で水の使われ方が変わると、上下水道などのインフラも劣化しやすくなります。さらに洪水・渇水の両方に備えが必要。
そこで鍵になるのが「測る」こと。
- 水循環基本法(2014)で“健全な水循環”を国の方針に。
- 2021年には地下水マネジメントを明記。**地下水位や量を「見える化」**して賢く使う。
- 2024年の能登半島地震では水インフラの脆弱さが露呈。平時からの備えが重要だと強調されました。
「測らないと、良くも悪くも“確かめようがない”」。データが、地域の合意づくりの土台になります。
「流域まるごと」で考える:治水×水利用×自然環境
河川だけ、上下水道だけ…の部分最適では限界。
天野さんは、流域治水・水の使い方・流域の環境保全を一体で設計する“流域総合水管理”を提案。
そして、自助・共助・公助のバランス、縦割りを超えた連携が欠かせません。
企業と森の力を借りよう:参加の“入口”が増えています
- 企業による森づくりを後押し。水源涵養(地下水を育てる力)を定量評価する手法を今年度中に公表予定。
→ 森がどれだけ水を蓄えるのか、数字で説明できるようになります。 - 国交省は「水循環企業登録認証制度(令和6年)」をスタート。
→ すでに89社が登録、10社がチャレンジ登録。ロゴマークの活用もOKで、企業の実践を見える化します。
研究者・自治体だけじゃない。企業や市民も参加できる“仕組み”が整いつつあります。
人の循環をつくる:「二地域居住」という選択肢
移住の“取り合い”ではなく、行き来そのものを増やす発想。
法律整備も進み、二地域居住の推進が本格化しています。
- 課題は住まい・なりわい・コミュニティの3つ。
- 具体策:空き家の改修活用、リモート就業の通信環境整備、集いの場や誘いの仕組みづくりなど。
- すでに全国で40地域以上が挑戦。自治体700超/企業・団体300超の全国プラットフォームも稼働中。
- 会場近隣では蘭越町・倶知安町が参画済。(留寿都の参加にも期待、とのメッセージ)
さらに、「ふるさと住民登録制度」も検討中。
二地域居住者をアプリで識別できれば、ごみ出しルールや地域ポイントなど、細かな運用がスムーズになります。
ひとりの町で抱え込まない:「地域生活圏」という考え方
合併ありきではなく、複数自治体が連携して生活サービスを面で維持する構想です。
民間事業者やNPOの力も借りながら、買い物・移動・医療・福祉・教育を越境して支える。
関連のリーディング事業も動いており、北海道はすでに複数案件で採択実績あり。今後もチャンスは広がります。
まとめ:小さく始めて、みんなで回す
天野さんの話は、どれも“自分ごとに引き寄せられる”視点でした。
- まず「測る」(地下水・流量・使い方)
- 流域まるごとで最適化(治水×利用×環境)
- 森・企業・市民の参加口を増やす(制度で後押し)
- 行き来を増やす(二地域居住で“人の循環”)
- 町どうしで面で支える(地域生活圏)
生活の安心と、地域のにぎわいは、水・人・経済の“循環”を同時に回すことで育ちます。
難しいことは、測る→共有する→小さく試すから。そこに“参加する仕組み”があれば、地域はもっと強く、しなやかになります。
聞き終えたあと、自分の町で何から測れるだろう? 誰と組めるだろう? と自然に手が動き出す。
そんな背中を押してくれる講演でした。