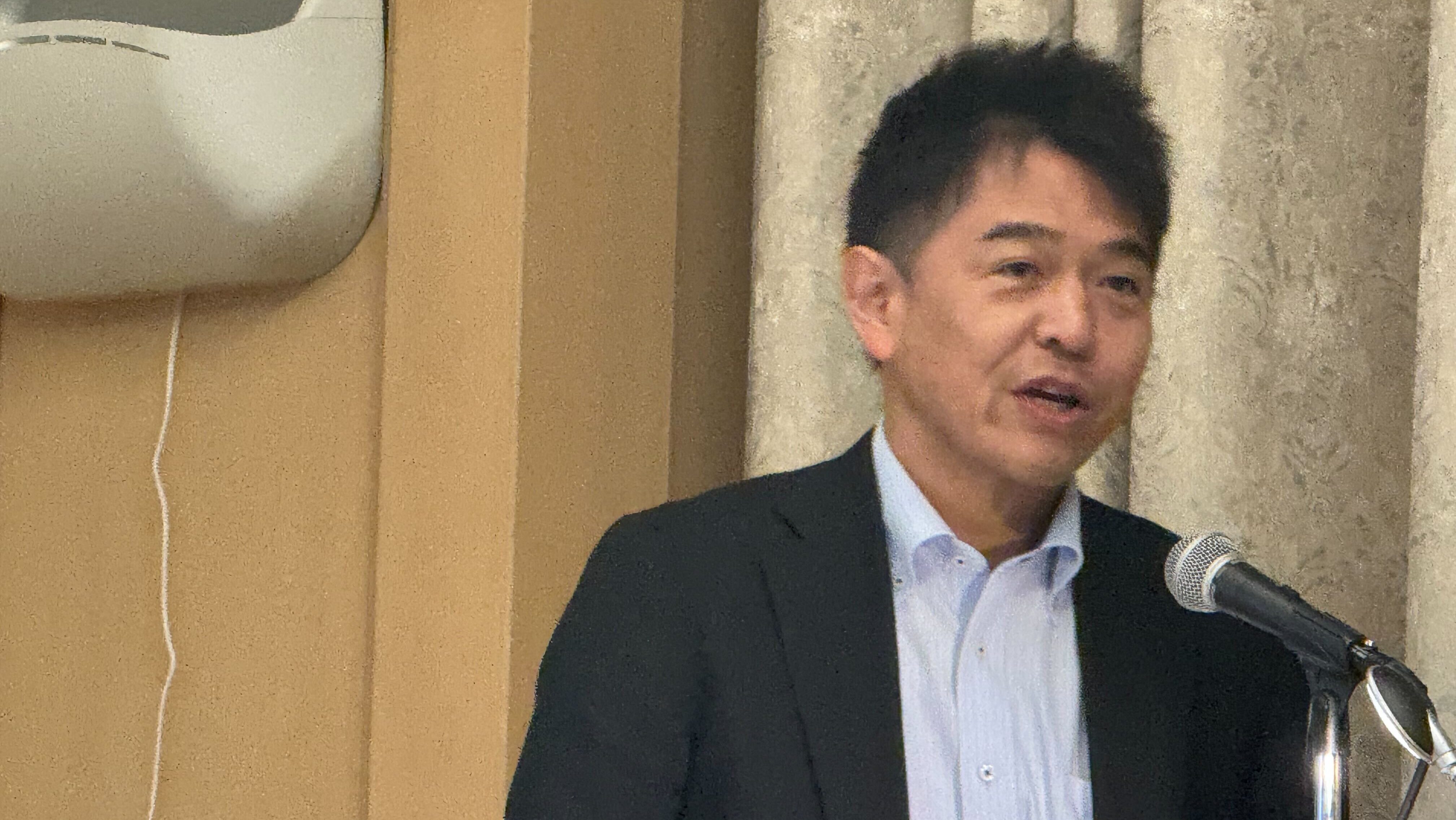島谷先生のお話を聞いて思ったこと
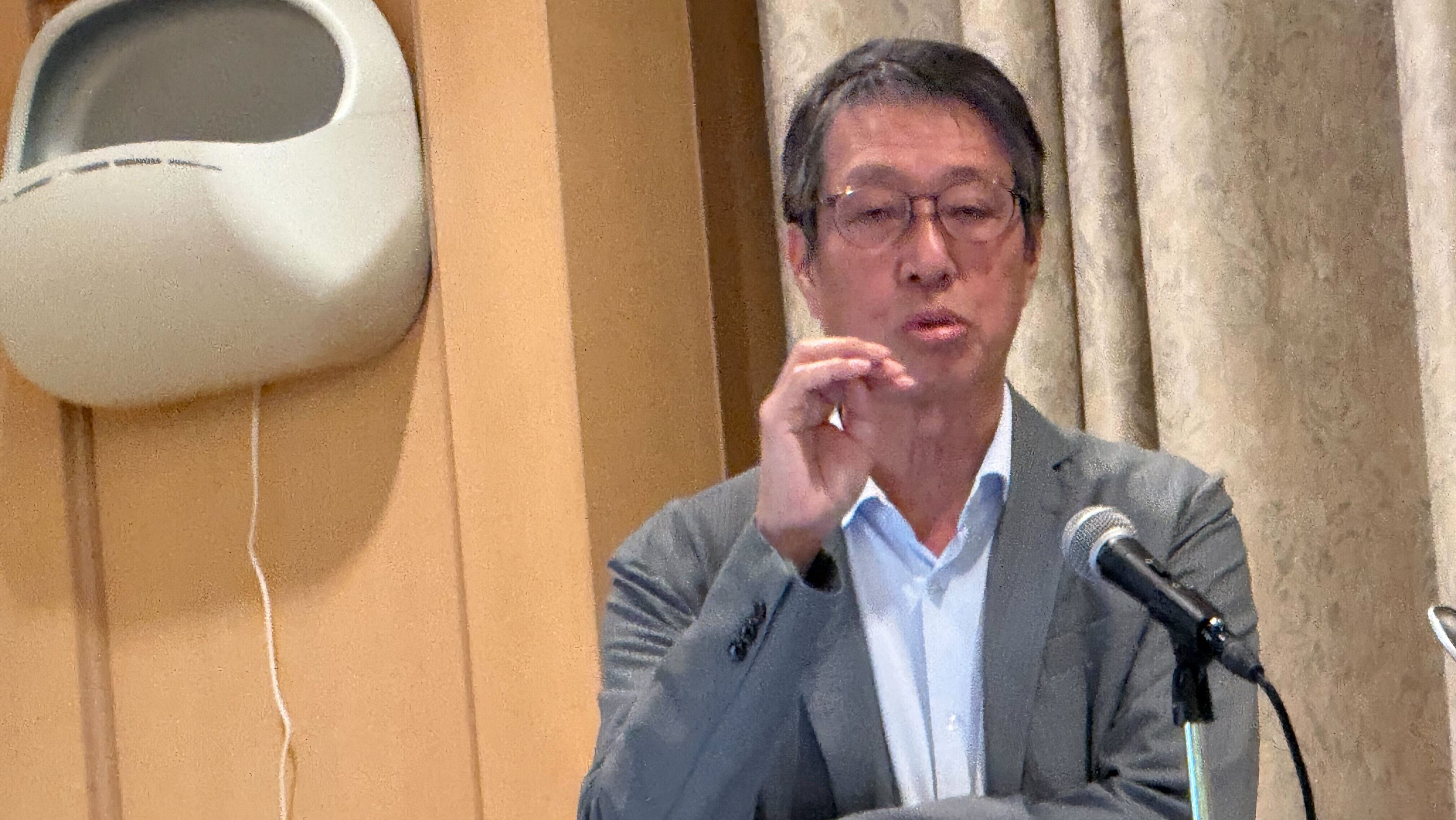
— 水をためて、しみこませて、ゆっくり流すしくみ
熊本県立大学・島谷 幸宏 先生のお話を聞いて
今回のシンポジウムでとても印象に残ったのは、熊本県立大学の島谷(しまたに)先生のお話です。
熊本での大洪水を例に、「川だけでなく、地域ぜんたいで水をゆっくり流すことが大切だ」と分かりやすく説明されました。
防災だけでなく、環境や地域の未来につながる取り組みだという言葉に強く心を動かされました。
グリーンインフラってなに?
島谷先生は「グリーンインフラ」という考え方を紹介してくださいました。
これは自然の力をいかして水害を防ぐ取り組みです。
- 雨庭(あめにわ):花だんや庭に雨水をためて、土にしみこませる
- 田んぼダム:田んぼに雨をためてからゆっくり流す
- リーキーダム:川に丸太などを組み、水の勢いをゆるめる
こうした工夫によって洪水をへらすだけでなく、地下水をふやしたり、生きもののすみかを守ったりできるのです。
雨と水の数字で分かること
島谷先生は、熊本の球磨川流域で大雨がふったとき、8億トンもの水が流域にふりそそいだと説明しました。
そのうち、約半分(50%)は森林や農地がためてくれたことも分かっています。
一方で、東京の杉並区の例では、雨水をためられるのはわずか15%ほど。自然の力がどれほど大きいかが数字で分かります。さらに、熊本県立大学の「雨庭」では、1年半で約93%の雨水が地下にしみこみ、川にあふれ出したのは100回の雨のうちわずか6回だけでした。
こうした結果から、雨水をうまく活かすことが洪水をへらし、地下水をふやすことにつながると学べました
みんなで取り組む仕組み
このプロジェクトは大学や役所だけでなく、銀行も大きな役割を担っているのが特徴です。
- 雨庭をつくった家庭や企業にローン金利の優遇を行う
- サステナ定期預金を作り、集まった資金を雨庭の活動に寄付
- 銀行の支店長が、地域の人に「雨庭づくり」を紹介
金融の力が加わることで、点の取り組みが地域全体へと広がっていきます。
協定で広がるつながり
熊本で始まった取り組みは、すでに沖縄や四万十川流域など全国へ広がりつつあります。
「協定(きょうてい)」という形で地域同士が約束し、技術・資金・人材を組み合わせることで、続けていける仕組みになっています。
私はこの話を聞いて、留寿都や羊蹄山ろくの町村もこの協定に入ったらすばらしいと感じました。北海道の自然や水を守るために、地域ぐるみでつながることが大きな力になるはずです。
まとめ
- 雨をためる・しみこませる・ゆっくり流す
- 自然と人、お金の仕組みを合わせて「地域ぐるみ」で取り組む
- 数字が示すように、自然の力は大きく、防災と環境を同時に守れる
島谷先生のお話から、「水をどう扱うか」が地域の未来を変えることを学びました。
これからの取り組みを、自分たちの町にも広げていけたらと思います。